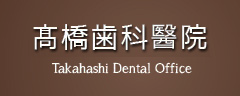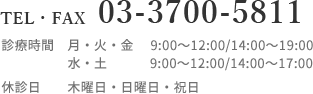新着情報(お知らせ・院長コラム)
- 髙橋歯科醫院[HOME]
- 新着情報(お知らせ・院長コラム)
- 老化する日本国、政治家は何を語るべきだろうか。
2025/07/20[院長コラム]老化する日本国、政治家は何を語るべきだろうか。
こんにちは
短い梅雨が明け酷暑の日が続いています。外気はまさしく殺人的な暑さです。みなさんくれぐれも体調管理に気をつけて下さい。

さて今日は参議院選挙です。またその先にはトランプ大統領の25%関税が現実味を帯びてきています。この流動的なさらにポピュリズム的極右翼政党が支持を伸ばす様な時代に日本国はどうあるべきなのでしょうか?そして政治家はこの国をどうの方向へ導くべきなのでしょうか。
人それぞれ思う政治や国の有り様は違うわけで、他の人々の思いを非難することは控えたいと思いますが、短絡的な主義主張に振り回されない様にしたいなとだけは思います。当然のことながら毎日の生活の苦しさや不安が払拭されなければその先のことなど考えられないでしょう。生きる上で最も大切な食の高騰や実質賃金の目減りは未来・将来に希望や展望をもてないという生きづらさにつながりまずは「この生活をなんとかしてくれ!」となるのはやむ得ないことだと思います。ただことはそれほど簡単ではないでしょう。

例えば今回の米騒動です。気候変動などの影響でお米の収穫量が想定以上に減少し主食であるお米が高騰し国民の不安と怒りが備蓄米の放出という緊急避難的な政策につながりました。そして石破首相は減反政策を転換し増産するとの方向性を打ち出しました。しかしながら、今まで減反していた田畑をいざすぐに増産とはいかない現実があります。とりあえず今年は異常気象の影響がなければ家畜飼料用に転作されていた分が主食用銘柄米に植え替えられ50万トンほど前年より増産になる様です。その一方でお米をはじめ食料安全保障上の自給率を上げるにせよその担い手になる農家の高齢化と少子化、離農は止めようがありません。さらに一度耕作を止めた水田は一度死んだ土地となっており息を吹き返えさせるためには膨大な時間とエネルギーが必要となりますし、トランプ関税などからアメリカ米などの輸入圧力を受ける中農水省は農業の大規模集約化を推奨していますが、山間地域の多い日本においては機械化や大規模化・効率化の難しい耕作地がほとんどであるという現実があります。一方お米の栽培において水田に稲の苗を植えるという従来の農法ではなくアメリカの様に畑に直接稲の種子を巻くという方が収穫量が増えるとの事から企業化した農法人では陸稲での耕作が進められていますが、果たしてそれでいいのでしょうか。水田は日本の原風景である里山の重要な生物サイクルを育むゆりかごであり、人工的に作られた湿原として多雨な日本での水の調整池として重要な役割を果たしています。そもそもお米の収穫に影響のある気候変動を私たちはどうしたらいいのでしょうか。エアコンのある部屋に篭ればいいのでしょうか。その電力はどうなるのでしょうか。

お米一つにしてもこれだけの多くの込み入った問題がありその解決は一朝一夕にはいかないでしょうしさらに流通や卸、精米などの問屋の問題などが複雑に絡み合っています。どこかをいじれば必ずどこかに皺寄せがいく様な様子になっています。トランプ関税で最たる問題になっている自動車産業もちょうど同じ様な構図がみられます。どちらの問題も短絡的な成果を求め小手先の政策では抜本的な解決はおろか問題を先延ばしにし中長期的にはより困難な状況を作ることになるでしょう。原発問題も然り、中国の海洋進出、台湾問題に絡みのアメリカ頼みの安全保障問題も然りではないでしょうか。

私たちの世界はそして日本は今多くの問題を抱えています。それらの問題は従来型の政治の有り様の延長で生じている問題であり、従来の考え方では解決できないことは明白です。日本においては特に戦後80年失われた30年といわれつつ経済大国としての成功体験から抜け出せずに問題を先送りにしてきたツケが回ってきていると思います。縮小していく国として、国民として真摯な覚悟と発想の転換が必要なのではないでしょうか。「この生活をなんとかするという事は今までの生活の延長上にはない」という事を政治家は語らねばなりません。